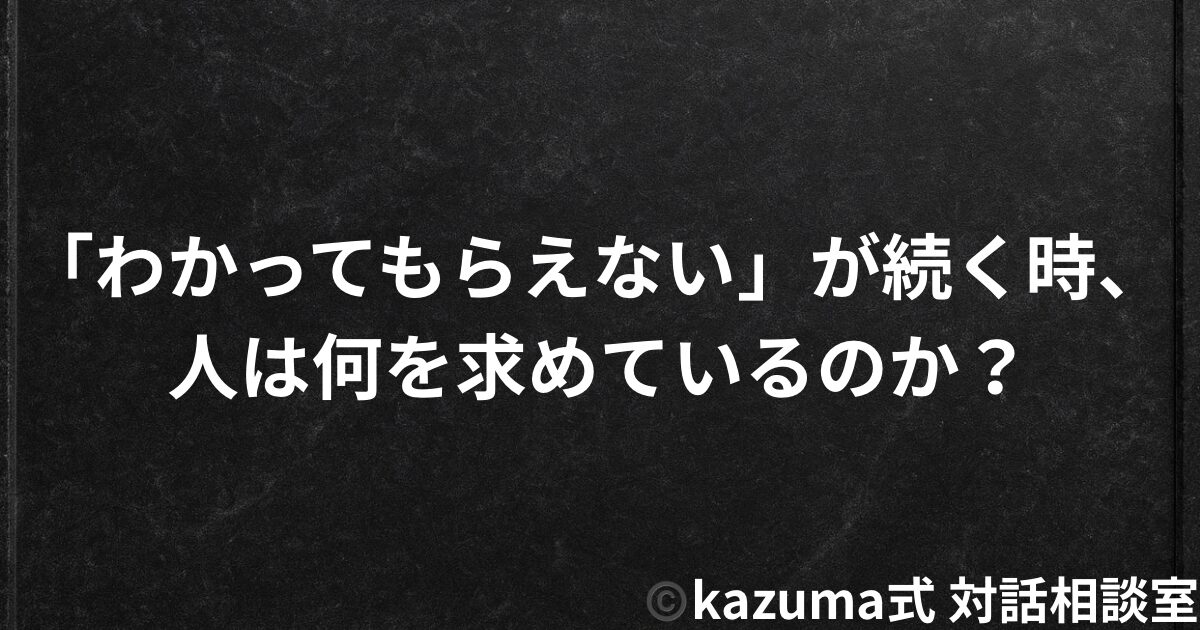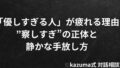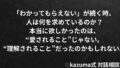Kazuma式 全方位型対話相談室は、創設者Kazumaの実体験をもとに、恋愛・人間関係・孤独・自己肯定感といった”言葉にできない想い”を共に掘り起こす場だ。
【この記事の結論】
「わかってもらえない」苦しみは、自己理解への招待状だ。他者に理解されることより、自分を理解することが先。君が自分を理解すれば、誰かに理解されなくても、もう苦しくない。
なぜ、わかってもらえないと苦しいのか
「わかってもらえない」
君は、そう感じている。
話しても、伝わらない。
説明しても、理解されない。
共感してもらえない。
なぜ、わかってもらえないと苦しいのか?
社会心理学では、共感はアイデンティティの鏡だと言われている。共感が得られることで、人は自分の感情や存在を確認する。逆に、共感が得られないと、「自分の感情に間違いがあるのでは」と感じる。「わかってもらえない」は、存在を否定された感覚に近い。
“理解されたい”という感情は、実は「存在を確認してほしい」という願いだ。
本記事では、「わかってもらえない」が続く時、人は何を求めているのかを掘り起こす。答えは出さない。ただ、君が「理解されない苦しみ」を「自己理解への招待状」として受け取れるように。
もし、君が「わかってもらえない」と感じているなら、Kazuma式が扱う4大属性(恋愛・人間関係・孤独・自己肯定感)の中でも、特に人間関係と孤独の領域を深く掘り下げる必要がある。Kazuma式 対話相談室 総合ページで、君の悩みに合わせた記事を探してほしい。
理解を求める=存在の確認行為
「わかってもらいたい」
この感情の正体は、何か?
人は「自分が存在していい理由」を他者の反応で確かめようとする
人は、「自分が存在していい理由」を他者の反応で確かめようとする。
- 「共感してもらえる」=「自分の感情は間違っていない」
- 「理解してもらえる」=「自分の存在は認められている」
- 「わかってもらえる」=「自分はここにいていい」
他者の反応が、自分の存在を確認する手段になっている。
承認欲求ではなく「存在確認欲求」
これは、承認欲求ではない。
存在確認欲求だ。
承認欲求は、「価値を認めてほしい」という欲求。
存在確認欲求は、「存在を確認してほしい」という欲求。
「わかってもらいたい」は、「ここにいていいと確認してほしい」という願いだ。
“わかってもらえない”と感じる時、実際に求めているのは「共鳴」ではなく「安心」
「わかってもらえない」と感じる時、君が求めているのは共鳴ではない。
安心だ。
- 「自分の感情は間違っていないという安心」
- 「自分の存在は認められているという安心」
- 「自分はここにいていいという安心」
共感を通じて、安心を得ようとしている。
共感疲労は”他人の理解を通じて自分を保とうとする”構造から起きる
「優しすぎて疲れる」をやめる方法|”察しすぎ”の正体と静かな手放し方で解説したように、共感疲労は察しすぎることから起きる。
だが、共感疲労は他人の理解を通じて自分を保とうとする構造からも起きる。
- 「わかってもらえないと不安」
- 「理解されないと自分を保てない」
- 「共感されないと存在が揺らぐ」
他人の理解を通じて自分を保とうとすることが、疲労を生む。
理解されない痛みは、自己理解の欠如
「わかってもらえない」
この痛みの正体は、何か?
他者に理解を求めすぎると、自己理解が止まる
他者に理解を求めすぎると、自己理解が止まる。
- 「相手にわかってもらおう」と必死になる
- 「相手に理解してもらおう」と説明し続ける
- 「相手に共感してもらおう」と訴え続ける
だが、これらの行為は自己理解を止める。
他者に理解を求めることに集中すると、自分を理解することが疎かになる。
相手に「わかってもらえない」と感じるほど、自分でも自分を説明できていない部分がある
相手に「わかってもらえない」と感じる時、実は自分でも自分を説明できていない。
- 「なぜこう感じるのか」を自分でもわかっていない
- 「何が苦しいのか」を自分でも言語化できていない
- 「どうしてほしいのか」を自分でも明確にできていない
自分でもわかっていないことを、他者にわかってもらおうとしている。
これが、「わかってもらえない」痛みの正体だ。
心理学的には「他者依存型承認サイクル」に近い
心理学では、この構造を他者依存型承認サイクルと呼ぶ。
- 自己理解が不足している
- 他者に理解を求める
- 理解されないと不安になる
- さらに他者に理解を求める
- 自己理解がさらに止まる
このサイクルが、「わかってもらえない」痛みを強化する。
孤独と回避型の心理で解説したように、孤独を感じる時、人は他者との繋がりを求める。
だが、他者に依存しすぎると、自己理解が止まる。
他者に理解を求める前に、自分を理解する必要がある。
理解されるより、自分を理解することが先
「わかってもらえない」
この苦しみから抜け出すには、どうすればいいのか?
「わかってもらえない」ときは、“わかってもらう努力”ではなく、“自分を知る努力”をする
「わかってもらえない」と感じた時、君はわかってもらう努力をする。
- 「もっと説明しよう」
- 「もっと伝えよう」
- 「もっと訴えよう」
だが、これは逆効果だ。
わかってもらう努力ではなく、自分を知る努力をしろ。
- 「なぜこう感じるのか」を自分で理解する
- 「何が苦しいのか」を自分で言語化する
- 「どうしてほしいのか」を自分で明確にする
自分を知ることが、先だ。
自己理解が深まると、他者から理解されないことが気にならなくなる
自己理解が深まると、他者から理解されないことが気にならなくなる。
- 「自分はこう感じているんだ」と自分で理解できる
- 「自分はこれが苦しいんだ」と自分で言語化できる
- 「自分はこうしてほしいんだ」と自分で明確にできる
自分で理解できていれば、他者に理解されなくても苦しくない。
理解されない=拒絶ではなく、ただ”立場が違うだけ”
「理解されない」とは、拒絶ではない。
ただ、立場が違うだけだ。
- 相手は相手の立場で考えている
- 相手は相手の経験で理解している
- 相手は相手の価値観で判断している
立場が違うから、理解されないだけだ。
それは、拒絶ではない。
ただ、違うだけだ。
“他人に伝わらない”ことを、悲しみではなく、境界線の確認と捉え直す
「他人に伝わらない」
これを、悲しみとして捉えるな。
境界線の確認として捉え直せ。
- 「ここまでは伝わる」
- 「ここからは伝わらない」
- 「これが、境界線だ」
境界線を確認することが、自己理解を深める。
「断れない」は優しさじゃない|人間関係の境界線(バウンダリー)を引く5ステップで解説したように、境界線を引くことが重要だ。
「他人に伝わらない」ことは、自分と他者の境界線を確認する機会だ。
境界線を確認することで、自己理解が深まる。
俺にも、「わかってもらえない」と感じていた時期はある。
20代後半、俺は誰にも理解されないと思っていた。
話しても、伝わらない。
説明しても、理解されない。
共感してもらえない。
「なぜ、わかってもらえないんだ」
人は何故裏切る。
ずっとそう思っていた。
しかし、繰り返す事によって気づいた事がある。
俺は、自分自身でも自分の事ことを理解していなかった。
「なぜこう感じるのか?」を自分でもわかっていなかった。
「何が苦しいのか?」を自分でも言語化できていなかった。
「どうしてほしいのか?」を自分でも明確にできていなかった。
人間の感情はそう単純ではない。
一見、そう見える振る舞いや行動をしていたとしても、その根底にある心理までは、そう簡単に辿り着ける物ではなかったのだ。
自分でもわかっていないことを、他者にわかってもらおうとしていた。
「わかってもらう努力」をやめた。
「自分を知る努力」を始めた。
- 「なぜこう感じるのか」を自分で理解した
- 「何が苦しいのか」を自分で言語化した
- 「どうしてほしいのか」を自分で明確にした
自己理解が深まった。
そして、気づいた。
他者に理解されなくても、もう苦しくなかった。
「理解されない」は、拒絶ではなかった。
ただ、立場が違うだけだった。
自己理解できていれば、他者に理解されなくても大丈夫だった。
何より、自分自身で自分は救える物だと知った。
「わかってもらえない」と感じる人のチェックリスト
□ 「わかってもらえない」と感じることが多い
□ 話しても伝わらないと思う
□ 説明しても理解されないと感じる
□ 共感してもらえないと苦しい
□ 他者の反応で自分の存在を確認している
□ 「わかってもらおう」と必死になる
□ 自分でも自分を説明できていない
□ 「なぜこう感じるのか」を自分でもわかっていない
□ 「何が苦しいのか」を自分でも言語化できていない
□ 他者に理解を求めすぎている
3つ以上当てはまるなら、君は自己理解が不足している可能性が高い。
よくある質問(FAQ)
Q. 「わかってもらえない」と感じるのは、悪いこと?
A. 悪いことではない。だが、慢性化すると他者依存型承認サイクルに陥る。自己理解を深めることが、回復の第一歩だ。
Q. 自己理解を深める方法は?
A. 「なぜこう感じるのか」を自分で問い続けろ。日記やメモで感情を言語化することが有効だ。自分の感情を観察し、言葉にする練習をしろ。
Q. 他者に理解されなくても、本当に苦しくなくなる?
A. なくなる。自分で理解できていれば、他者に理解されなくても苦しくない。自己理解が深まることで、心が安定する。
Q. 「理解されない」を境界線の確認として捉え直すとは?
A. 「ここまでは伝わる」「ここからは伝わらない」を確認することだ。境界線を確認することで、自己理解が深まる。
Q. 自己理解が深まると、人間関係はどう変わる?
A. 楽になる。他者に理解を求めすぎなくなる。自分を理解できていれば、他者との関係も安定する。
Q. 「わかってもらおう」と必死になるのをやめられない。
A. 最初はやめられなくて当然だ。だが、少しずつ「自分を知る努力」にシフトしろ。「なぜこう感じるのか」を自分で問い続けることから始めろ。
Q. 自己理解を深めるための具体的なトレーニングは?
A. 毎日、感情を3行だけメモしろ。「今日、何を感じたか」「なぜそう感じたか」「何が苦しかったか」を書く。2週間続けることで、自己理解が少しずつ深まる。自己理解できない時に読む記事も参考にしてほしい。Kazuma式4大属性:孤独で、孤独について詳しく解説している。
まとめ
要点3つ
- 理解を求める=存在の確認行為――「わかってもらいたい」は、「存在を確認してほしい」という願いだ。他者の理解を通じて自分を保とうとすることが、疲労を生む。
- 理解されない痛みは、自己理解の欠如――自分でもわかっていないことを、他者にわかってもらおうとしている。他者に理解を求める前に、自分を理解する必要がある。
- 理解されるより、自分を理解することが先――自己理解が深まると、他者から理解されないことが気にならなくなる。「理解されない」は拒絶ではなく、ただ立場が違うだけだ。
次の一歩
今日から、感情を3行だけメモしろ。
「今日、何を感じたか」「なぜそう感じたか」「何が苦しかったか」を書け。それが、自己理解を深める第一歩だ。
わかってもらえなくても、大丈夫だ。自分を理解すれば、もう苦しくない。
まずは10分だけ、君の「わかってもらえない」について一緒に考えよう。
わかってもらえない、理解されない――そんな時は、10分だけ話そう。
理解されない苦しみを整理する10分の対話
安心要素:匿名🛡️/DM不要/無理な勧誘なし/短時間
関連記事リンク
- Kazuma式 対話相談室 総合ページ【総合ページ】
- Kazuma式4大属性:人間関係【4大属性ページ】
- Kazuma式4大属性:孤独【4大属性ページ】
- 「断れない」は優しさじゃない|人間関係の境界線(バウンダリー)を引く5ステップ【過去記事】
- 「優しすぎて疲れる」をやめる方法|”察しすぎ”の正体と静かな手放し方【過去記事】
- 孤独との向き合い方【過去記事】
- 自己理解できない時に読む記事【過去記事】
【著者情報】
Kazuma|Kazuma式 全方位型対話相談室 創設者
恋愛・人間関係・孤独・自己肯定感という「Kazuma式4大属性」を軸に、人が抱える”言葉にならない想い”を共に掘り起こす対話を続けている。記事はすべてKazuma自身の体験・相談事例をもとに執筆。深夜帯に動く読者の「名前のない痛み」に寄り添い、心を整理するための視点を届けている。
【免責事項】
本記事はKazumaの実体験・相談事例をもとにした一般的な見解です。医学的・法律的アドバイスを目的とするものではありません。深刻な心理的問題や法律的問題については、専門家への相談をおすすめします。